ピロリ菌とは
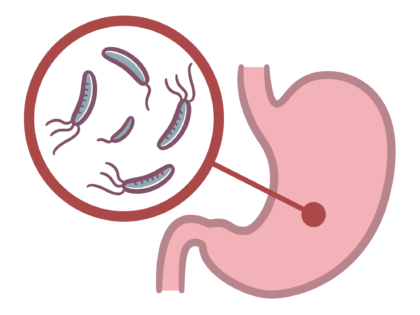 ヘリコバクター・ピロリ菌(Helicobacter pylori)ことピロリ菌は、人の胃粘膜に生息し、強い酸性の環境下でも生息できる細菌です。慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、胃ポリープなどの発症・誘発の原因とされています。世界保健機関(World Health Organization:WHO)は2014年に、世界中の胃がんの80%がピロリ菌によるものと報告し、除菌が胃がん予防に有効であると報告しています。
ヘリコバクター・ピロリ菌(Helicobacter pylori)ことピロリ菌は、人の胃粘膜に生息し、強い酸性の環境下でも生息できる細菌です。慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、胃ポリープなどの発症・誘発の原因とされています。世界保健機関(World Health Organization:WHO)は2014年に、世界中の胃がんの80%がピロリ菌によるものと報告し、除菌が胃がん予防に有効であると報告しています。
日本では、成人の約半数がピロリ菌に感染していると推定され、感染が確認次第、除菌治療を受けるよう推奨されます。感染の有無を調べる検査と除菌治療は保険適用となりますが、健康保険適用には、条件を満たす必要があります。早期胃がんやピロリ菌関連の慢性胃炎が胃カメラ検査で見つかった場合、または胃潰瘍・十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病の治療を受けている場合は、検査や除菌治療が保険適用とされます。
それ以外では自費診療となりますので、詳細はお問い合わせください。
年齢が上がると
感染率が高まるピロリ菌
ピロリ菌は口を通じて感染することが知られており、衛生状態の不十分な地域では感染率が高い一方で、先進国では低い傾向にあります。しかし、日本は先進国でありながらも感染率が高いという特異な状況にあります。過去の研究によりますと、日本人の感染率は年齢層によって異なり、40代以上では高く、10代~20代では低い傾向がみられます。これは、衛生環境の向上が影響していると考えられます。将来的には感染率がさらに減少すると予測されていますが、現在でも日本人の約半数が感染しており、若年層においても完全には根絶されていないため、油断は禁物です。
ピロリ菌の感染経路は口からの感染が主であるものの、その他の経路や予防策につきましては未だに明らかになっていません。
また多くの場合、免疫力が低い乳幼児期に感染するとされ、世代ごとの感染率の違いは、それぞれの乳幼児期の上下水道の普及率に起因すると考えられています。現在、日本では衛生環境が改善されたことにより、ピロリ菌の感染率は大幅に低下しており、今後もこの傾向が続くと見込まれています。
ピロリ菌の診断方法
ピロリ菌の感染を確認する方法は2つあり、内視鏡を使用した検査とその他の方法があります。
内視鏡検査で行う場合
 胃カメラ検査は胃の内部を直接見て病状を把握でき、検査中に、胃の粘膜の組織を採取することが可能です。迅速ウレアーゼ検査を通して、ピロリ菌の存在が確認できます。
胃カメラ検査は胃の内部を直接見て病状を把握でき、検査中に、胃の粘膜の組織を採取することが可能です。迅速ウレアーゼ検査を通して、ピロリ菌の存在が確認できます。
迅速ウレアーゼ検査
ピロリ菌が生成するウレアーゼという酵素は、尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解する働きをしています。この反応を利用した迅速ウレアーゼ検査では、胃粘膜の組織をアンモニアで反応する試薬に入れ、色の変化を見てピロリ菌の感染を判断します。
内視鏡検査以外の検査
内視鏡を使わないピロリ菌検査もあります。除菌治療後に行う、除菌成功の評価として用いられることもあります。
抗体検査
ピロリ菌に感染すると体内で抗体が生成されます。これは、血液や尿、唾液で検出可能です。これらのサンプルを分析することで、感染の有無が調べられます。
便中抗原検査
便に含まれるピロリ菌の抗原を検出することで、感染の有無を確かめることができます。
ピロリ菌の除菌治療
 ピロリ菌に感染していることが判明した際は、除菌治療を受けることを推奨します。この治療は薬を飲む薬物療法で、治療が終わった後には、除菌の成否をチェックします。一次除菌治療の成功率は約90%で、もし失敗した場合でも、二次除菌治療で80%の成功率が期待されます。保険適用の除菌治療は、二次除菌までとなります。また、ピロリ菌による病気がある場合は、除菌治療前にその病気を先に治療する必要があります。
ピロリ菌に感染していることが判明した際は、除菌治療を受けることを推奨します。この治療は薬を飲む薬物療法で、治療が終わった後には、除菌の成否をチェックします。一次除菌治療の成功率は約90%で、もし失敗した場合でも、二次除菌治療で80%の成功率が期待されます。保険適用の除菌治療は、二次除菌までとなります。また、ピロリ菌による病気がある場合は、除菌治療前にその病気を先に治療する必要があります。
除菌の効果を判定する呼気試験を行うためには、検査当日は飲食を控えて来院する必要があります。
1診断
胃カメラ検査を行って粘膜の状態を詳細に確認し、組織を採取(生検)してピロリ菌感染の有無を確かめます。
陽性の場合
健康保険適用による除菌治療を行います。
陰性の場合
除菌治療は必要ありません。
症状や病変がある場合には状態に合わせた治療を行いますが、特に問題がなければ診療は終了となります。
21回目の除菌治療
ピロリ菌を除菌する2種類の抗生剤、抗生剤の効果を高める胃酸分泌抑制薬を処方します。
服薬は、1日2回を1週間行っていただきます。
3除菌判定
服用終了から一定期間が経過してからピロリ菌感染の有無を調べ、除菌が成功したかどうかを確かめます。
ピロリ菌の有無を調べる検査を再度行い、治療によってピロリ菌が除菌されたかどうかを確認します。
陽性の場合
健康保険適用による2回目の除菌治療が可能です。
陰性の場合
除菌が成功し、除菌治療は終了となります。
ただし、過去にピロリ菌感染の経験がある場合は、除菌に成功しても胃がんの発症率はゼロにはならず、感染経験のない方に比べるとリスクが高い状態です。定期的に胃カメラ検査を受けることで早期発見できれば、生活や仕事に支障を及ぼさずに完治が望めます。
42回目の除菌治療
抗生剤1種類を変更し、その他は1回目の除菌治療と同様の服薬を1週間行います。
5除菌の判定
服薬から一定期間経過したら、ピロリ菌が除菌されたかどうかを判定する検査を行います。
陽性の場合
自費診療となりますが、3回目の除菌治療も可能です。
診察、検査、薬剤代を合わせて30,000円程度の費用がかかります。
アナフィラキシー、蕁麻疹、嘔吐、下痢、口内炎、味覚障害、肝障害、腎障害、頭痛、めまいといった副作用が発現する可能性もあります。
陰性の場合
除菌が成功し、除菌治療は終了となりますが、ピロリ菌感染経験がある場合には、除菌に成功しても胃がんの発症率はゼロにはならず、感染経験のない方に比べるとリスクが高い状態です。
定期的に胃カメラ検査を受けて早期発見できれば、生活や仕事に支障を及ぼさずに完治が望めます。
除菌治療の副作用
ピロリ菌治療薬によるアレルギー反応として、皮膚の発疹やかゆみ、腹痛を伴った下痢、血便、発熱などが起こる恐れがあります。これらの症状が出た場合は、直ちに薬の服用を止めて、医師の診察を受けてください。
報告されている副作用としては、軟便、下痢、味覚異常、肝機能検査値の変動(AST(GOT)、ALT(GPT))などが挙げられますが、通常は薬の服用を止めると自然に解消します。しかし、症状が重い場合は、医師に相談することが必要です。
さらに、除菌治療後に胸焼けなどといった、逆流性食道炎の症状が現れることがあります。これは、治療中に飲んでいた胃酸分泌抑制薬の服用を止めた結果、胃酸の分泌が正常化されることで起こるものです。











