過敏性腸症候群(IBS)について
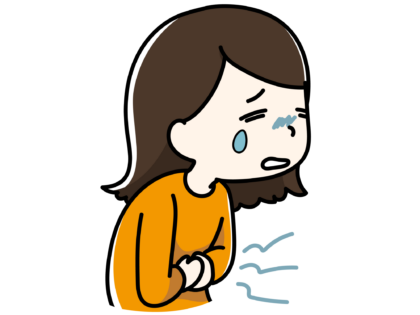 過敏性腸症候群(IBS)は、消化管に潰瘍や炎症などの異常が起こっていないにも関わらず、便秘、下痢、腹痛、膨満感といった症状が現れる病態です。
過敏性腸症候群(IBS)は、消化管に潰瘍や炎症などの異常が起こっていないにも関わらず、便秘、下痢、腹痛、膨満感といった症状が現れる病態です。
消化管の働きは自律神経によって調節されているので、大きなストレスや緊張が過敏性腸症候群を引き起こす一因となることがあります。
過敏性腸症候群の原因
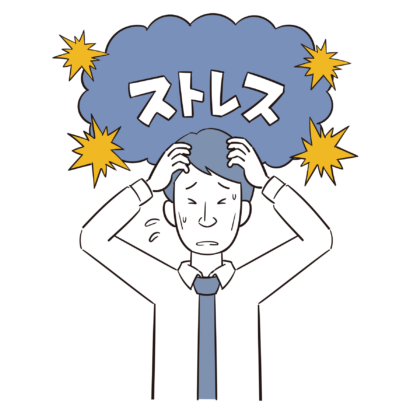 腸の動きが不規則になることによって、消化器の症状を引き起こします。消化器の働きは自律神経によって大きく左右されるため、ストレスや不安、過労、睡眠不足、環境の変化などがトリガーとなって発症することが多いと考えられています。しかし、明確な原因は現在のところ特定されていません。
腸の動きが不規則になることによって、消化器の症状を引き起こします。消化器の働きは自律神経によって大きく左右されるため、ストレスや不安、過労、睡眠不足、環境の変化などがトリガーとなって発症することが多いと考えられています。しかし、明確な原因は現在のところ特定されていません。
過敏性腸症候群の症状
症状に応じて、以下のようにタイプが分けられます。
下痢型
急な水様性の下痢と強い腹痛が特徴で、排便によって一時的に痛みが和らぎます。この腹痛と下痢は、1日に何度も起こります。
心理的ストレスが発症のトリガーとなることが多く、症状の再発への恐れがストレスをさらに増大させることもあります。早期治療へ繋げることで、症状の改善が見込めます。
便秘型
 便秘をはじめ、腹痛、残便感、排便困難などの症状が現れます。強くいきむことで、いぼ痔や切れ痔のリスクが上昇してしまう可能性があります。
便秘をはじめ、腹痛、残便感、排便困難などの症状が現れます。強くいきむことで、いぼ痔や切れ痔のリスクが上昇してしまう可能性があります。
交代型
激しい腹痛を伴う下痢と便秘が交互に現れます。
その他
腹鳴(ふくめい:お腹がグルグル・グーグー鳴る)、膨満感、ガス(おなら)漏れなど、排便とは関連しない症状が起こることもあります。
過敏性腸症候群の検査・診断
 症状が現れた時期やトリガー、便通の頻度、便の見た目、持病や病歴、食生活、日常の生活スタイルなどについて詳しくお聞きします。症状の原因を特定するために、大腸カメラ検査や血液検査を通して、炎症や他の病気の有無を確かめることがあります。
症状が現れた時期やトリガー、便通の頻度、便の見た目、持病や病歴、食生活、日常の生活スタイルなどについて詳しくお聞きします。症状の原因を特定するために、大腸カメラ検査や血液検査を通して、炎症や他の病気の有無を確かめることがあります。
Rome Ⅲ基準
Rome Ⅲ基準による診断では、大腸内視鏡検査で炎症や他の病変が見つからない場合、以下の条件を満たすと過敏性腸症候群と診断されます。
- 排便により症状が軽減される
- 症状が出ると排便の回数に変化が生じる
- 症状が出ると便の形状が変わる
過去3ヶ月の間に、上記の症状が2つ以上存在し、1ヵ月に3日以上、繰り返されるようでしたら、確定診断をくだします。
過敏性腸症候群の治療
生活習慣の改善
 過敏性腸症候群(IBS)の治療では、生活習慣の見直しが基本となります。食事はバランス良く、決めた時間に摂り、刺激物の摂取を避けるよう勧めています。また、十分な水分と食物繊維を確保することも大切です。適度な運動によってストレスを軽減し、睡眠の質を高めることも重要です。趣味やリラクゼーションを通じて、ストレスをうまく解消させることも良いでしょう。
過敏性腸症候群(IBS)の治療では、生活習慣の見直しが基本となります。食事はバランス良く、決めた時間に摂り、刺激物の摂取を避けるよう勧めています。また、十分な水分と食物繊維を確保することも大切です。適度な運動によってストレスを軽減し、睡眠の質を高めることも重要です。趣味やリラクゼーションを通じて、ストレスをうまく解消させることも良いでしょう。
薬物療法
個々の症状や体質に合わせた薬を処方します。治療の効果は個人差があるため、再診によるフォローアップを通して、患者様の症状の変化に合った処方になるよう適宜調整します。












