長く続く便秘でお困りの方へ
 正常な便には約80%の水分が含まれており、これ以上多くなると軟便または下痢に、少なすぎると便秘になります。便秘は、水分摂取が不足したり、腸での吸収が過剰になって水分の含まれる量が減ったりすることで便が硬くなり、排便しにくくなることで起こります。また、便意を我慢する習慣も、便意を感じにくくして便秘を招く原因になります。消化から排便までの時間は個人差があり、ほとんどの場合は24時間程度とされています。毎日排便がなくても無理ないきみがなく、排便後に快適な状態になっている場合は、特に問題はありません。
正常な便には約80%の水分が含まれており、これ以上多くなると軟便または下痢に、少なすぎると便秘になります。便秘は、水分摂取が不足したり、腸での吸収が過剰になって水分の含まれる量が減ったりすることで便が硬くなり、排便しにくくなることで起こります。また、便意を我慢する習慣も、便意を感じにくくして便秘を招く原因になります。消化から排便までの時間は個人差があり、ほとんどの場合は24時間程度とされています。毎日排便がなくても無理ないきみがなく、排便後に快適な状態になっている場合は、特に問題はありません。
便秘は、排便すると痛くなったり、力を入れないと排便できなくなったりするなどのトラブルがある状態、もしくは排便をした後でも便が体内に残っているように感じる状態です。運動不足や食物繊維の不足が原因で起こることが多いですが、胃腸の病気が原因で生じるケースもあります。
病気にかかっていない状態でも便秘が長引くと、腸内で有害物質ができやすくなり、体調不良を引き起こすことがあります。体調不良による便秘は一時的に起こり得ますが、慢性的な便秘や、下痢と便秘を繰り返す場合は、医療機関へ相談してきちんと根治を目指していきましょう。
便秘の原因
便秘は、便の水分不足や、排便機能の低下によって起こるのではないかとされています。便秘には、腸の機能障害によって起こる「機能性便秘」と、腸の病気によって起こる「器質性便秘」、内分泌疾患(糖尿病など)や神経疾患などといった、全身疾患の症状として起こる「症候性便秘」があります。そして、薬の副作用によって起こる「薬剤性便秘」もあります。
機能性便秘
機能性便秘には、弛緩性、痙攣性、そして直腸性の3つのタイプがあります。
弛緩性便秘
弛緩性便秘は、大腸の運動機能の低下により起こる便秘です。主な原因としては、運動不足、水分不足、過度なダイエット、食物繊維の不足などが挙げられます。
蠕動運動の減少によって便が溜まったり、便の水分が過剰に吸収されたりすることで起こります。この結果、便は硬く太くなり、排便に支障をきたしやすくなります。
便が長期間大腸内に留まると、腸内の細菌によって腐敗や発酵が進みます。それによりガスや有毒物質が生成され、腹部の不快感や肌荒れなどの全身症状を引き起こすことがあります。
痙攣性便秘
ストレスや過労などによって自律神経が乱れた結果、副交感神経が活発になり、腸が緊張状態に陥ることで起こる便秘です。このため、力を入れないと排便が困難になり、排便した後でも便が体内に残っているような感覚を覚えたり、下腹部が痛くなったりすることがあります。
便は小さく固まり、ウサギの糞のような形状になることがほとんどです。便秘と下痢を繰り返す便秘症に多いタイプで、過敏性腸症候群の便秘型や混合型の方にもよくみられます。
直腸性便秘
結腸をゆっくり通過した便は直腸へ一時保管されます。そして量が一定に達すると、便意が発生します。便意があると、脳は自律神経によって制御される内肛門括約筋を緩めて、排便を促します。
もう1つの肛門括約筋である外肛門括約筋は、意識的にコントロールされており、便が漏れないように締める役割を担っています。しかし、トイレに行けない状況で便意を我慢する習慣がつくと、便意を自覚しにくくなり、直腸性便秘が起こりやすくなります。直腸性便秘は、高齢者や痔の痛みで便意を我慢する方によくみられる便秘です。
便が直腸に長く留まると、排便が困難になります。特に、痔による痛みによってトイレに行くのを我慢する癖がつくと、直腸性便秘になりやすくなります。
器質性便秘
大腸がんやポリープの進行によって腸の通路が狭まると、便秘が生じることがあります。腹部手術後の癒着や、クローン病などによる腸閉塞も、便秘の原因となります。
通常、便秘にならない方が急に便秘を経験し、それが持続したり、強い腹痛・血便・悪心・嘔吐を伴っていたりする場合は、迅速な治療が必要になります。
器質性便秘にかかった時、便秘薬や下剤を用いた強制的な排便を行うと、症状がさらに悪化しやすくなります。そのため治療では、原因の特定と適切な治療が求められます。
便秘を伴う病気
 大腸の病気によって便の流れが妨げられてしまう器質性便秘の原因としては、腸閉塞、大腸癌、大腸ポリープ、大腸憩室症、潰瘍性大腸炎、クローン病などが挙げられます。
大腸の病気によって便の流れが妨げられてしまう器質性便秘の原因としては、腸閉塞、大腸癌、大腸ポリープ、大腸憩室症、潰瘍性大腸炎、クローン病などが挙げられます。
さらに、大腸以外の臓器や神経系、内分泌系疾患によって症候性便秘を引き起こすことがあります。具体的に言いますと、代謝異常(甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症、低カリウム血症、高カリウム血症など)や、神経系の問題(神経損傷、糖尿病神経症など)、精神疾患(うつ病や摂食障害など)が原因で生じる便秘もあります。特に女性では、骨盤臓器脱や子宮筋腫も原因の1つとされています。
また、痔と便秘は密接な関係があります。便秘による硬い便が裂肛を引き起こしたり、痔の痛みによって排便を避けたりすることで、直腸性便秘の発症・悪化を招くことがあります。
さらに、過敏性腸症候群の中でも便秘型や混合型は、痙攣性便秘と似たメカニズムによって便秘を引き起こすものです。これらの病気は、適切な治療を行わないと重症化する恐れがあります。
機能性便秘も同様に、軽視すると腸内の便が溜まり続け、発酵や腐敗によるガスや毒素が体に悪影響を及ぼす危険性があります。便秘の原因を明確にし、根本的な治療を受けるためにも、市販薬に頼る前に専門医の診断を受けることが重要です。
便秘の検査と診断
 問診では、便秘の始まった時期、どういった症状があるのか、全身の健康状態、過去の病歴、現在服用されている薬について、詳しく伺います。お話しいただく内容の正確さが、原因解明の鍵となりますので、遠慮なく詳細をお聞かせください。
問診では、便秘の始まった時期、どういった症状があるのか、全身の健康状態、過去の病歴、現在服用されている薬について、詳しく伺います。お話しいただく内容の正確さが、原因解明の鍵となりますので、遠慮なく詳細をお聞かせください。
その後は、腹部の聴診と触診を実施し、血液検査、腹部超音波検査、腹部X線検査を通じて腸やその周りにある臓器、血管の状態をチェックします。必要に応じて大腸カメラ検査も行い、腸の粘膜状態やポリープ、がんなどの異常、狭窄の有無を調べます。大腸カメラ検査では、ポリープが見つかればその場で切除可能です。また疑わしい病変が見つかった場合は、その組織を採取し、病理検査にて確定診断をくだすことができます。
当院では、内視鏡専門医が最新の内視鏡システムを用いて、患者様の負担を最小限に抑えつつ、丁寧かつ迅速、正確な検査を提供していきます。どうぞ安心してご相談ください。
便秘の治療
器質性便秘や症候性便秘に対しては、それぞれの根本となる病気に対する治療が必要です。薬が原因の便秘の場合は、処方されている薬の変更を検討します。
一方、機能性便秘では、薬物療法だけでなく生活習慣を見直すことで、改善を図っていきます。
薬物療法
便秘治療薬には、様々なタイプが存在します。便を柔らかくするために水分を増やす薬や、便の量を増加させる薬、大腸の運動を促進する薬、小腸での水分吸収を調節する薬などがあります。
また、腸内環境を整えるサプリメントや、有効とされる漢方薬を処方することもあります。患者様の便秘の種類や生活習慣に応じて、最適な薬を選択します。
再診時には薬の効果をお伺いしながら、必要に応じて用量の調整や薬の変更を行い、細やかな治療を心がけています。
生活習慣の見直し
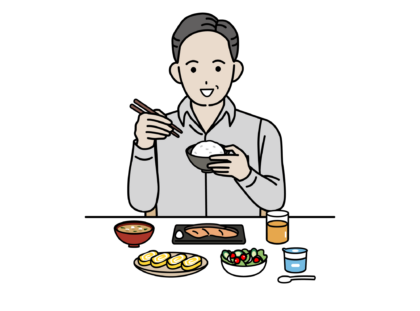 便秘の再発を防ぐためには、食生活の改善、規則正しい生活習慣の確立、健康的なダイエットの実践が不可欠です。薬の使用を中止する前に、これらの要因を解決することが重要です。
便秘の再発を防ぐためには、食生活の改善、規則正しい生活習慣の確立、健康的なダイエットの実践が不可欠です。薬の使用を中止する前に、これらの要因を解決することが重要です。
患者様のこれまでの生活習慣を踏まえ、適切な食事や運動の指導を行いながら、無理のないダイエット方法や適切な排便習慣についてアドバイスします。ご不明な点やご質問があれば、どんなことでもお尋ねください。













