げっぷ
げっぷとは
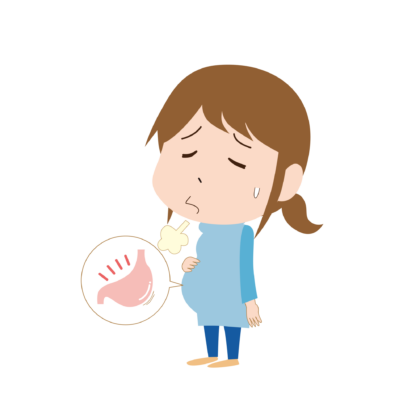 げっぷは通常、無害な生理現象ですが、頻繁に発生する場合は注意が必要です。以下のようなげっぷには特に注意しましょう。
げっぷは通常、無害な生理現象ですが、頻繁に発生する場合は注意が必要です。以下のようなげっぷには特に注意しましょう。
注意が必要なげっぷ
緊急性が高くないげっぷ
- 早食いをした後に発生するげっぷ
- 炭酸飲料を摂取した後のげっぷ
ストレスによって胃腸の動きが鈍くなり、げっぷが増えることもあります。
受診が必要なげっぷ
- 胸焼けや胃もたれを伴うげっぷ
- 長期間続くげっぷ
げっぷは様々な要因で発生しますが、通常は心配する必要はありません。しかし、腹痛や胃もたれを伴っていたり、長期間続いたりしている場合は、消化器内科の受診をお勧めします。
げっぷを伴う消化器疾患
食道裂孔ヘルニア
胃の一部が食道裂孔から食道側へ飛び出している状態です。胃と食道を繋ぐ境目が緩むことで、胃酸が逆流しやすくなります。
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流して、食道の粘膜に炎症を引き起こす状態です。げっぷ以外にも、胸焼けや胃の不快感、喉の異常感などの症状がみられます。
機能性ディスペプシア
消化管の粘膜に異常が起こっていないのにも関わらず、胃の痛みや膨満感、胃もたれ、吐き気などの症状が現れる病気です。胃酸の過剰分泌や胃・食道粘膜の知覚過敏が原因であるとされています。過去には自律神経失調症と診断されてきました。
呑気症
無意識のうちに空気を過剰に摂取してしまうことで、げっぷやお腹の張りが生じる状態です。早食いやストレスも、この症状を引き起こす要因となります。
げっぷが多い方への検査
胃カメラ
 げっぷだけでなく、胸焼け、胃の痛み、吐き気などの症状がある場合は、早期に胃カメラによる検査を受けることが必要です。
げっぷだけでなく、胸焼け、胃の痛み、吐き気などの症状がある場合は、早期に胃カメラによる検査を受けることが必要です。
当院では、鎮静剤を用いた内視鏡検査を通じて、痛みを最小限に抑えながら消化器系疾患の早期診断・治療を行っています。
げっぷでお困りなら当院までご相談ください
 当院の消化器内科では、長引いているげっぷに対する診断、検査、治療を提供しています。げっぷは一般的な生理現象ですが、放置すると重要な病気を見落とす可能性もあります。
当院の消化器内科では、長引いているげっぷに対する診断、検査、治療を提供しています。げっぷは一般的な生理現象ですが、放置すると重要な病気を見落とす可能性もあります。
当院の胃カメラ検査は、消化器内視鏡学会認定の専門医が実施し、高精度な検査と正確な診断・治療を提供していきます。どんな些細な症状でも、遠慮なくご相談ください。
おなら
おならでお悩みの方へ
おならは、肛門から排出されるガスです。通常は飲み込んだ空気や消化する過程で生成されたガスから成り立っています。
自然な生理現象として起こりますが、ガスが多く溜まってしまうと、おならの頻度が増加することがあります。また、食べ物の種類によっては、おならの臭いが強くなることもあります。ガスが増える病気が隠れている可能性もあるので、おならの回数や臭いが気になる場合はぜひ、お気軽にご相談ください。
おならが増える原因
食物繊維が豊富に含まれる食品
食物繊維は健康に良い影響を与えますが、イモ類や豆類など繊維質の多い食品を過剰に摂取すると、腸内ガスが多くなることがあります。
食物繊維が大腸で分解された後、水素やメタンガスが作られますが、これらのガスは無臭です。食物繊維は便通を整える作用があるので、ガスが多くなっても心配する必要はありません。
タンパク質やニンニクなどの食品
タンパク質やニンニク、玉ネギなどを多く摂ると、消化しきれない分が大腸で分解され、悪臭を放つガスが生成されます。これは、ウェルシュ菌などの悪玉菌によるタンパク質の腐敗が原因で、アンモニアや硫化水素、二酸化イオウ、スカトールなどが発生することで、臭いが強いおならを引き起こします。
便秘
 便秘で便が腸内に溜まると、ガスも排出されず、蓄積されてしまいます。これらのガスは腸内細菌によって発酵され、強い臭いを持つおならとなります。
便秘で便が腸内に溜まると、ガスも排出されず、蓄積されてしまいます。これらのガスは腸内細菌によって発酵され、強い臭いを持つおならとなります。
さらに、これらのガスは腸管から吸収され、血液を通じて肺へ運ばれます。呼吸とともに排出されるため、口臭の原因にもなります。
ストレス
ストレスを感じていると、無意識に空気を多く飲み込むことがあります。それにより、腸内ガスが増加してしまいます。
何らかの病気
まず過敏性腸症候群が挙げられます。過敏性腸症候群は下痢型と便秘型といったタイプに分かれている病気ですが、中にはガスが増えるタイプもあります。また、大腸がんの進行によって便秘が生じ、それがおならの増加に繋がることがあります。
慢性胃炎を含む他の消化器疾患でも、おならが増えることがあります。
おならを伴う疾患
呑気症
呑気症は、過剰に空気を飲み込んでしまう状態です。普段から無意識に空気を呑み込んでいますが、ストレスや早食い、口呼吸によって、呑気症になることがあります。
慢性胃炎
胃の粘膜の炎症が長く続いてしまう病気で、胸焼け、胃痛、吐き気といった症状の他、膨満感やげっぷ、おならの増加なども引き起こします。
放置すると、胃潰瘍や胃がんのリスクを上昇させる萎縮性胃炎へと進行する可能性があるため、適切な治療が不可欠です。
過敏性腸症候群
腸に病変(炎症など)がないのにも関わらず、便秘や下痢、腹痛、腹部の張りなどの慢性的な症状を引き起こす病気です。消化管内のガスが原因で、おならが増えて腹部が張ってしまうこともあります。
ストレスなどの影響を受けると発症しやすく、腸の機能や知覚過敏などが症状に関与しているのではないかと言われています。
大腸がん
大腸がんは、進行すると便の通過を妨げ、便秘や下痢を引き起こすことがあります。これにより、お腹の張りが生じることがあります。早期発見が重要ですので、気になる症状がありましたら消化器内科の受診をお勧めします。
日常生活でできる予防法
食生活の見直し
 タンパク質やニンニク、玉ネギなどの食べ過ぎに注意し、悪臭の原因となる悪玉菌を抑えましょう。また、ヨーグルトや乳酸菌飲料、漬物、オリゴ糖などを摂取して善玉菌を増やし、腸内フローラを健全に保つことも有効です。
タンパク質やニンニク、玉ネギなどの食べ過ぎに注意し、悪臭の原因となる悪玉菌を抑えましょう。また、ヨーグルトや乳酸菌飲料、漬物、オリゴ糖などを摂取して善玉菌を増やし、腸内フローラを健全に保つことも有効です。
ガスが溜まるのを予防する
便意を感じた際は、すぐにトイレへ行くように心がけましょう。水分と食物繊維を適切に摂取して便秘を予防し、腸内環境を改善しましょう。
また、運動をこまめに行うと代謝が促進されます。その結果、血流が良くなり、腸の働きも改善されやすくなります。
ストレスの解消
ストレスは自律神経のバランスを乱し、自律神経によって調整されている腸の機能にも影響を与えてしまい、腸内ガスを増加させる原因となります。
また、おならの増加が症状としてみられる過敏性腸症候群のように、ストレスが症状を悪化させる病気もあります。腹部の張りやおならの増加はストレスをさらに高めるため、リラックスできる趣味やスポーツ、旅行などを通じて、定期的にストレスを解消することが大切です。
おならの対処法
当院では、おならや腹部のガスを含む消化器系の症状に対して、専門的な治療を提供しています。おならは自然な生理現象ですが、時には何らかの病気が原因で頻繁に出てしまうこともあります。
「おならが多くなった」という悩みはなかなか相談しにくいですが、出る回数が多くなると、社会生活に支障をきたすこともあります。お悩みの方は、遠慮なくご相談ください。












